相対思考を利用したマーケティングのワナ|自分で考える習慣を失うとお金も失う
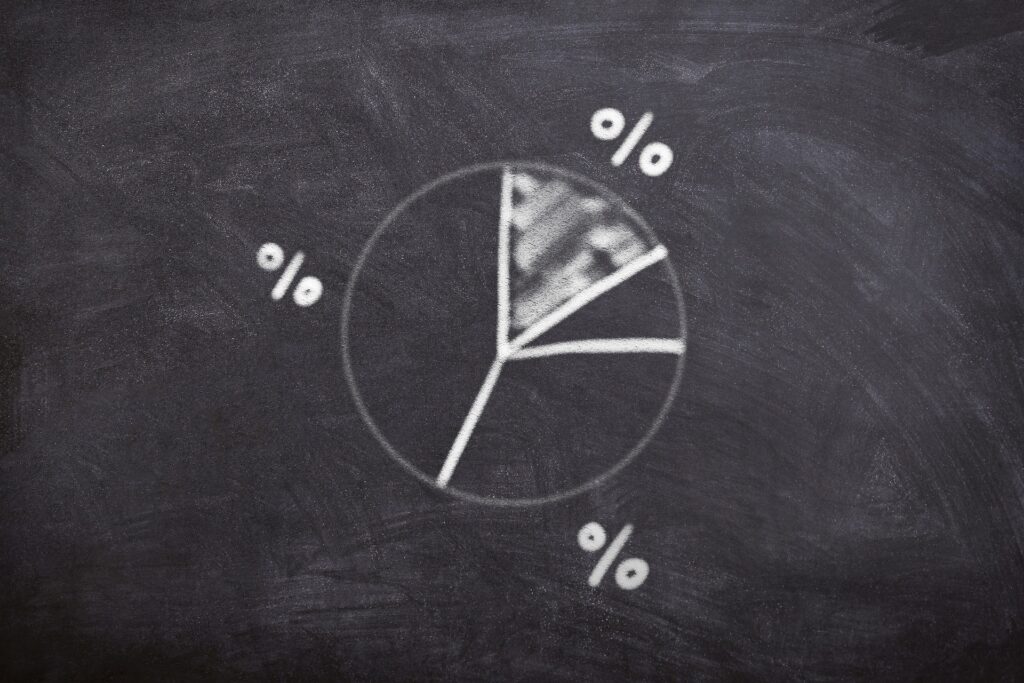
あなたは確たる判断基準を持ってお金を使うことが出来ていますか?
恐らく自信を持って「イエス」と答えられる人は少ないでしょう。
そして実際に多くの人は、自分の判断で支出を行ったと思い込まされています。
マーケティング戦略は、人間の心理の弱点を巧妙に利用したものが多く、中でも相対思考の利用は顕著です。
人間が支出の判断を誤りやすいポイントはこちらのページで解説しています。
どんな戦略やワナが仕掛けられているかを知ることは、適切な判断を行う上で非常に有効な対策です。
このページでは相対思考とそれを利用した代表的なマーケティング手法について解説します。
相対思考とは?

早速ですが、質問です。
一本の直線が描かれていたとして、その直線は長いでしょうか?短いでしょうか?
恐らく多くの人が「何と比べて?」と思うことでしょう。
これこそが相対思考です。
何かの良し悪し、大きい小さい、高い安いといった判断をする時、いつも無意識のうちに何かと比較しています。
そのものの絶対的な大きさより、比較やパーセンテージで考えてしまう思考ということです。
物事を比較対象なしに絶対的に判断するためには、自分の基準を持っていなければならず、それは非常に脳の負担になります。
相対思考とは、そういった様々な判断を簡単に行うための工夫、脳のショートカット機能の1つです。
平均値などの統計的な指標を参照してしまう傾向も、この相対思考が関係しています。
この相対思考は非常に便利な考え方ですが、これにばかり頼り過ぎているせいで、多くの人がマーケティングのワナにハマってしまっています。
以降では、この相対思考というクセを利用したマーケティング手法について解説します。
大きく分けると以下の4つです。
①アンカリング効果 ②感応度低減性 ③人気商品 ④ダブルバインド
順番に解説していきます。
①アンカリング効果

アンカリング効果は相対思考の最も典型的な例です。
アンカーとは船の錨のことで、相対思考が大好きな「基準点」になります。
最も身近な例で言うとセール品の価格表示です。
セール価格の横に元値が記載されていることが多いと思います。
こうすることで元値がアンカーになり、どれだけ安くなっているかを強調することが出来ます。
「セールで2,000円です!」とだけ表示されても、多くの人はモノの価値と価格を適切に比較できないので、これがお買い得なのか分かりません。
これを考えること自体がめんどくさくなるため、そのままでは買わないという選択肢を採られてしまいます。
しかし元値とセール価格の比較なら簡単です。
「通常4,000円のところ、セールで2,000円です!」と言われれば、「50%引きなら安い!」と判断してくれるわけです。
因みにアンカーは元値など関係するものの価格である必要はありません。
それを利用したマーケティング手法がダウンセルというものです。
10万円の商品の商談に失敗した時そこで諦めるのではなく、すかさず2万円くらいの商品を薦めます。
今まで悩んでいた10万円という価格がアンカーになっているため、それに比べるとかなり安く感じてしまい買いやすくなるのです。
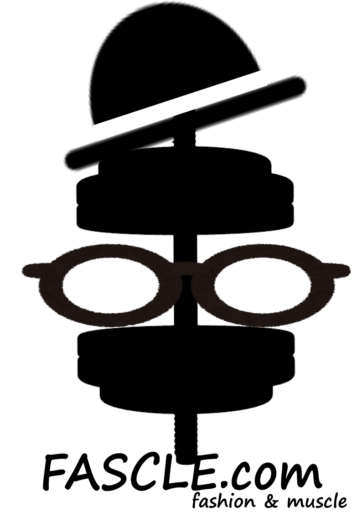
スーツの代わりにネクタイとか革靴を薦めたり、時計の代わりにネクタイピンを薦めるとか色々あるよね
因みに全く価格と関係ない社会保障番号(日本で言うマイナンバーみたいなもの)などの数字もアンカーになり得るという研究もあります。
②感応度低減性

感応度低減性も相対思考が顕著に現れている例です。
言葉自体には馴染みが無いという人が多いかもしれませんが、聞けば心当たりがあると思います。
簡単に言えば、同じ100円でも対象となる商品の値段によってその重要性が大きく変わるという現象です。
ケース1:ニンジンを買う場合
最初に入った店は1袋100円
次に入った店は1袋200円
ケース2:PCを買う場合
最初に入った店は110,000円
次に入った店は110,100円
恐らく多くの人がケース1では最初の店に引き返しますが、ケース2では2軒目で購入してしまうでしょう。
どちらのケースも同じ100円の節約ですが、検討してる価格帯に比べるとその割合は大きく異なります。
つまりパーセンテージで判断しており、まさに典型的な相対思考の現れです。
この感応度低減性はケース2のような家や車の購入などの高額な買い物のシーンでよく利用されています。
家や車本体の価格に比べると数万円のオプションは非常に安く見えるため、多くの人が簡単に契約してしまうことでしょう。
お金に無頓着な人だけでなく、ケース1のように日頃から小さな節約を心掛けてるようなタイプでも騙されてしまうので気をつけてください。
③人気商品
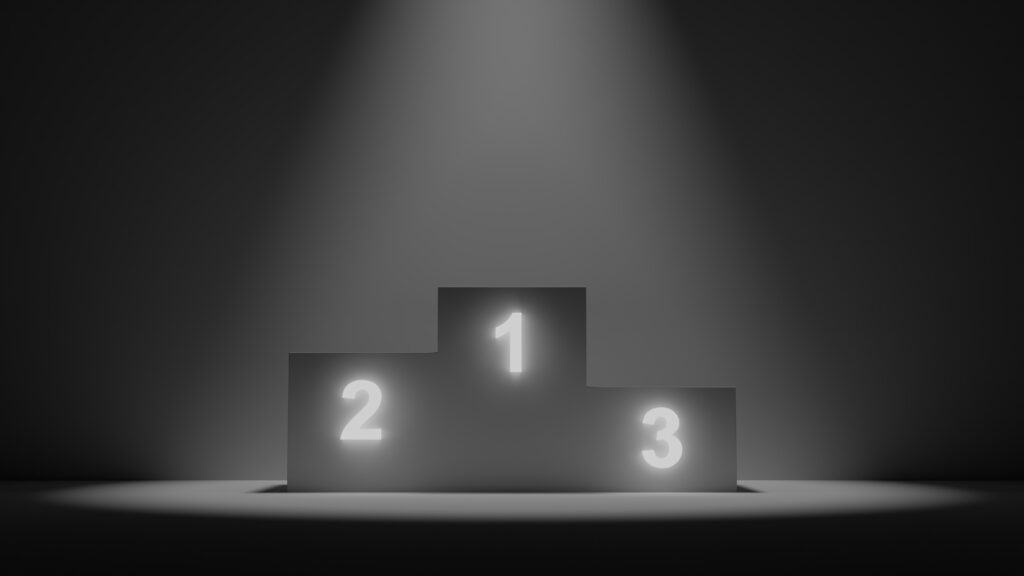
購入する商品や飲み会のお店選びなどでは、レビューサイトの評価やランキングを参考にする人が多いと思います。
実店舗でも「人気ナンバーワン」「売れ筋商品」みたいなポップをよく見かけますよね?
選択肢がありすぎて判断できない時、人は「みんなはどれを選んでるんだろう?」と世間の評価を参照するのです。
このようにみんなが良いと言ってるものなら良いはずという思考のショートカットを社会的証明と言います。
因みに人間は希少性が高いモノにも惹かれる傾向がありますが、これも「みんな欲しがってるんだ」という思考が理由です。
自分で判断できない時に「世間一般ではどうなんだろう?」と考える典型例が平均値や中央値などの統計指標を当たることです。
これらが全く参考にならないというわけではありませんが、あなたがすべきことの正解を教えてくれるわけではありません。
20代の平均貯蓄額が154万円と知って、155万円貯めたとしても何の解決にもならないでしょう。
さらにこうした世間一般を基準に判断するクセが付いた結果として「普通」という信仰から抜け出せなくなってしまいます。
当然のことながら、この「普通」という基準も平均値と同じくあなたが求めてる答えではありません。
詳しくは以下のページで解説していますが、「普通」を追うことで財布は軽く心は重くなってしまいます。
④ダブルバインド

最後に紹介するのはダブルバインドという手法です。
これは異性を口説く時に利用される心理テクニックとして有名なので、聞いたことがある人もいるかもしれません。
簡単に言うと、選択肢を用意することでそのどちらも選択しないという選択肢を意識の外に追い出してしまう方法です。
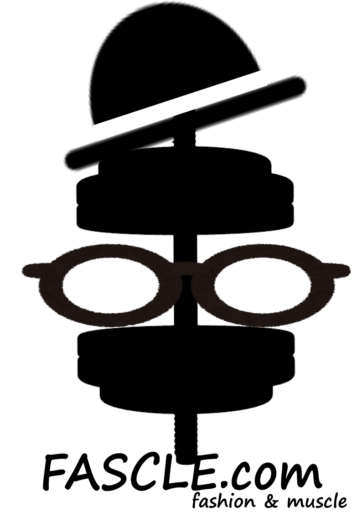
「あのホテルとこのホテルだったらどっちが良い?」ってやつね
ダブルバインドを実践するためには、いくつかのグレード・選択肢を用意しておくだけです。
たったこれだけのことで「買わない」という第3の選択肢が頭に浮かびにくくなってしまいます。
何故なら商品Aと商品Bには共通点があるので相違点を比べるという簡単な判断で済みますが、買わないという選択肢は商品A・Bとは異質で比較が難しいからです。
合コンやアイドルグループなどを想像すると分かりやすいかもしれません。
全く顔のタイプが異なると、全体のステータスを使って絶対評価をしなければいけないので大変です。
しかし似た系統の人が数人いると、その内の誰かを選ぶ確率が高くなります。
判断の基準が出来るので順位付けがしやすくなり、自分にとっての1位を選び出しやすくなるからです。
合コンに行く時は自分と系統が似てるけど、ちょっと自分が勝ってるくらいの人を連れてくと人気者になりやすいでしょう。
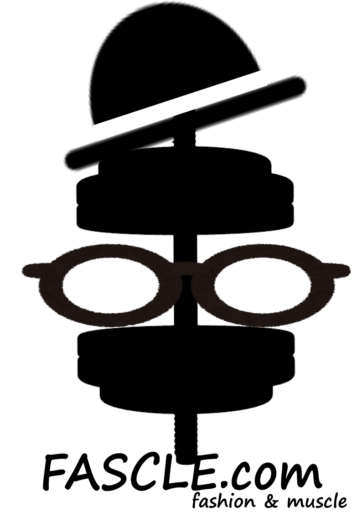
引くほど性格悪い戦略だからたぶん友達なくすよ?
まとめ 相対思考にどう対応するか?
人間の特徴的な心理の1つである相対思考とそれを逆手に取ったマーケティング手法について解説しました。
絶対評価というのは非常に頭を使うので、何かを手掛かりに良い・悪い、高い・安い、大きい・小さいなどを把握しようとします。
あらゆる判断を絶対評価で行うことは流石に非効率的ですが、あまりに自動操縦に乗り過ぎるとお金をむしり取られることになりかねません。
相対思考を利用したマーケティング手法に対抗する一番の方法は自分なりの判断の軸を持つこと、価値観を明確にすることです。
とは言え自分の価値観と社会的な刷り込みを区別することはけっこう難しく、買い物の度に判断するのも大変だと思います。
そのため、そもそも買い物の機会自体を減らすという選択が個人的にはベストです。
まず本当に有効なお金の使い道というのは、そんなに多くありません。
さらに買い物の機会を減らすこと自体にもメリットがあり、このことについては別のページで解説しています。
準備中
価値観で対抗することはあくまで次善の策であり、それも出来ないなら「マーケティングのワナにかけられてないか?」と警戒心を持つしかないでしょう。
てなとこで。
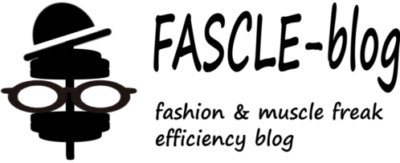








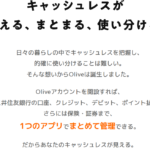
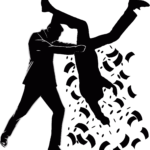








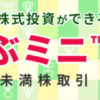

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません