本を読むメリット・重要性|効率的でムダのない読書法【本は無限・時間は有限】
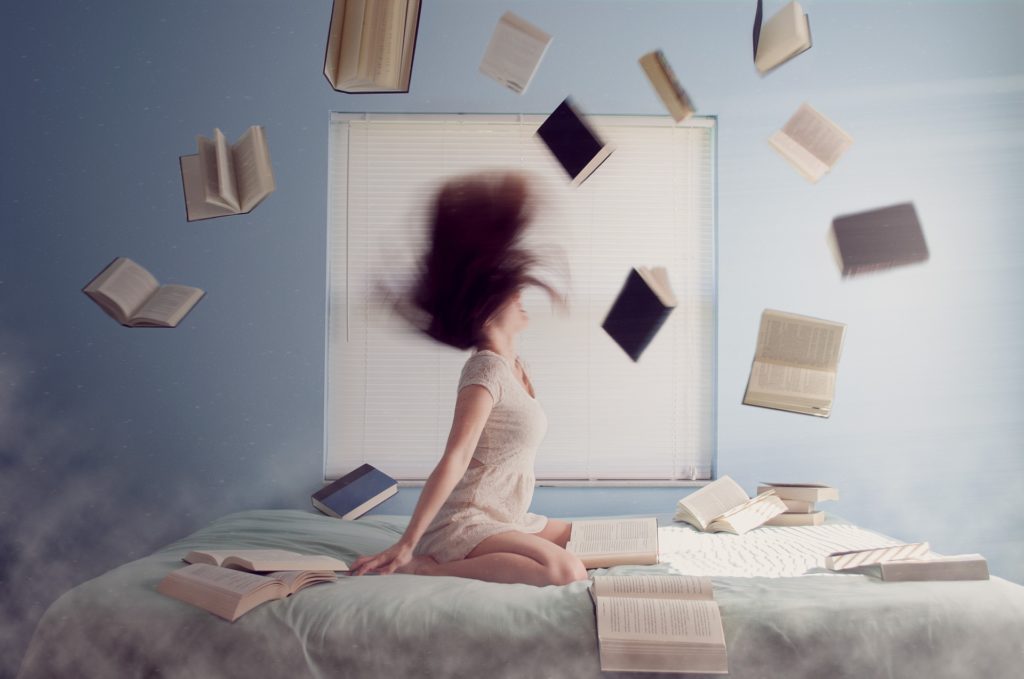
皆さんは日頃、読書をする習慣はあるでしょうか?
読書を含めた社会人の勉強時間の平均はなんと1週間で6~7分と言われています。恐ろしいほど低い数字ですね…。
かく言うぼく自身は社会人になってから、読書や勉強が毎日の習慣になりました。
恐らくは学生の頃にサボってしまって失った時間を取り戻そうとしてるのでしょう。
月にだいたい10冊くらいは通勤の往復だけで読むようにしています。
本を読んで知識を得ることは非常に効率的なのでオススメの習慣です。
しかし闇雲に読んでいてもその恩恵を十分には得られません。
このページでは、読書をする意義・メリット、効果的な本の選び方から読み方までトータルで解説します。
1 本は効率性の塊
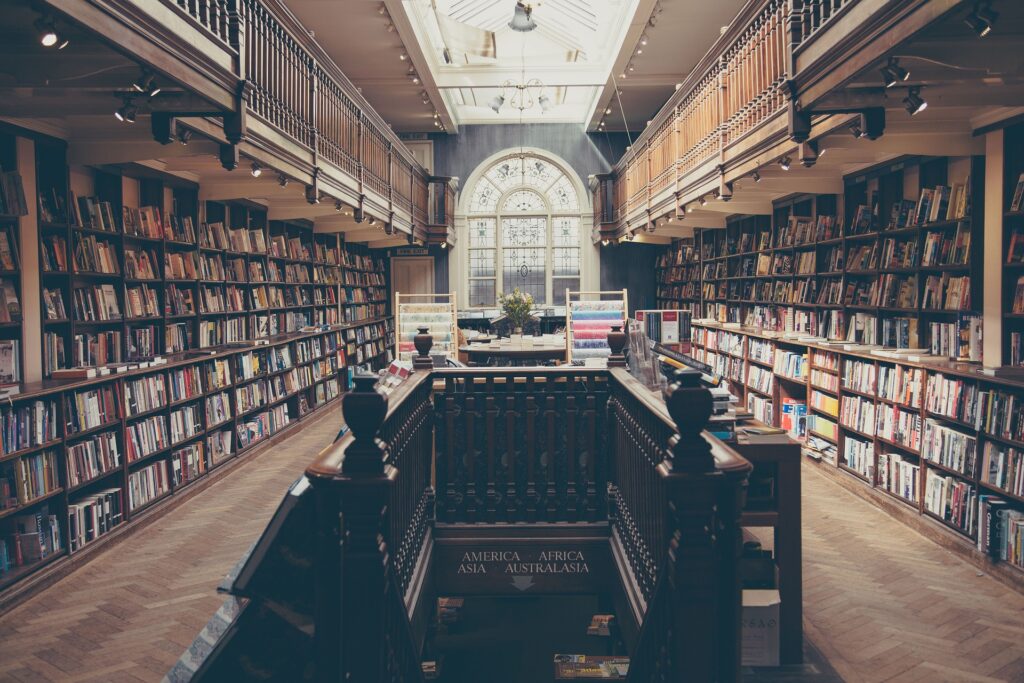
まずそもそも読書習慣がない人向けに、読書をすることのメリットについて簡単に解説します。
1-1 巨人の肩に乗って世界を見る
自分の身一つで一生に経験・研究できることはたかが知れてますが、本には著者が時間をかけて知り、考え、整理してきたものが詰まってます。
このことを端的に表した「巨人の肩に乗る」という比喩は、論文検索エンジンのGoogle Scholarの標語としても有名です。
忙しくて本を読む時間なんてない、という人も多いかもしれません。
しかしたった数時間かけて本1冊を読むだけで、1人分の経験値(知)が手に入ると考えてみたらどうでしょう?
複数の研究や論文を統合して分析したメタアナリシスなら一気に数十人、数百人の知恵にもなります。
また優秀な経営者や科学者などに一般人が直接会う機会に恵まれることはまずありません。
セミナーや講演会に出席するとなればそれなりのお金もかかります。
しかし本であればそうした制約なく、たったの1,000円~2,000円のコストと数時間で彼らの言葉・考えに触れることが出来るのです。
経験の幅に限界があると述べましたが、その狭さは考え方や価値観の狭さにも直結します。
そうした知識、経験、考え方の幅を拡げるという意味で、こんな効率の良い方法はありません。
1-2 インプットの重要性
「アイデアが降ってきた」という表現をするので、天命のようなものと勘違いしてる人がいます。
しかし実際はこれまでに記憶した膨大な情報を無意識下でつなぎ合わせた結果として出てくるものです。
知らないもの・知らない場所に対して、欲しいとか見てみたいとか行きたいなどと思わないのと同様に、0から1は絶対に生まれません。
何事にもまず考えるための基礎となる材料が必要です。
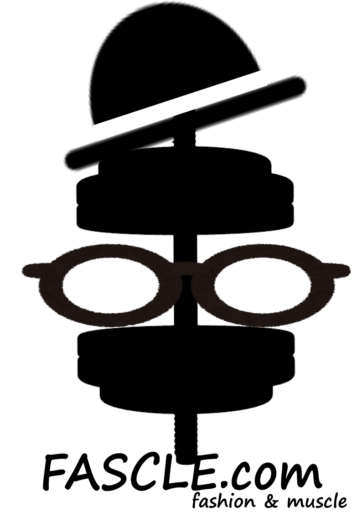
脳はあくまでも超高性能の記憶装置だからね
また新しいインプットをしている最中にそれがキッカケになってアイデアが浮かんで来ることがあります。
アウトプットを呼び起こす刺激を与えるという点でも定期的に新しい情報を脳にインプットすることが重要なのです。
因みに当然のことながら情報のインプットは基礎であって、それだけでアイデアが生まれることはありません。
アイデアを効果的に生み出す方法、創造性の鍛え方についてはこちらのページで解説しています。
1-3 スキルの獲得にも繋がる
読書から得られる知識というのは個別の本のテーマに関する知識だけではありません。
様々な文章を読むことで自然とライティング力がついてくるのです。
最初は何となく読んでるだけという人が多いでしょう。
しかし徐々に「語尾が単調でくどいな」「説明の順序が悪くて論理性・説得力がないな」「これって確実にそうだって言える?」と文章の良し悪しを見分けられるようになってくるものです。
そしてその審美眼がそのままライティングスキルに繋がります。
文章を書く力というのはビジネスにおいて非常に重要なスキルです。
どんなに優れたアイデアがあっても、プレゼンや交渉の場で相手に上手く伝えられなければ、それは無いも同然と言えます。
またメールでのやり取りが増える昨今、文章力が無いと何度も説明し直すハメになったり、生じた誤解が原因でトラブルになることもあるかもしれません。
本業のビジネスだけでなく、ブログやウェブライター、執筆活動などライティング力が活きる副業は沢山あります。
これからの時代、会社からの給料に依存して生きるのは好ましくありません。
会社から放り出された時に手元に残っているのが、その会社でしか活きない知識・技能だけならビジネスマンとしての市場価値はゼロです。
汎用性が高く副業収入にも繋がるスキルを手に入れられるというのも1つ読書の大きなメリットと言えるでしょう。
2 ネットより本の方が良い理由
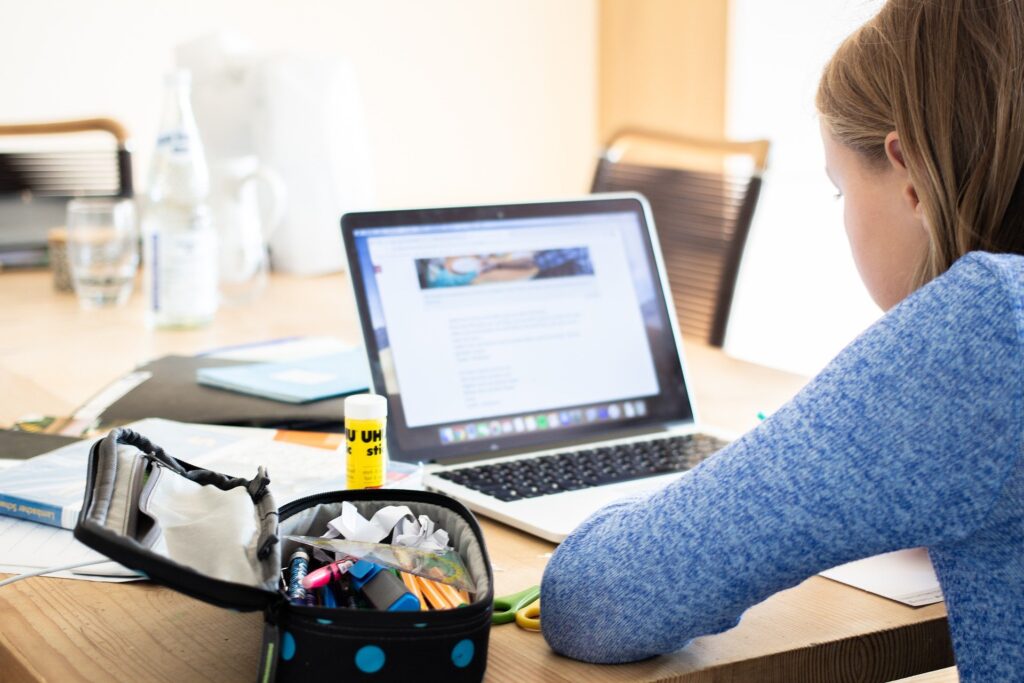

YouTubeの要約とか無料ブログじゃダメなの?
最近ではブログやYouTubeなどのメディアに本の要約や様々な分野に関する知識が掲載されていて、無料で見ることが出来ます。
そのため、こうした媒体で見る方がコスト的にも時間的にも効率的だと考える人もいるでしょう。
しかし知識習得の効率化という点ではあまりオススメしません。
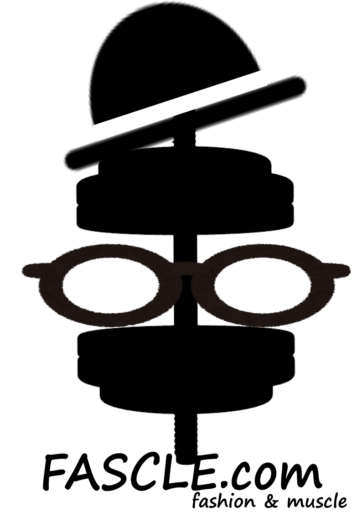
ネットで記事書いてる人が言うのもおかしな話だけどね
理由は以下の2つです。
①知識の吸収にやや難がある
②重要性は人によって異なる
2-1 知識の吸収効率に難あり
ネット上の無料の情報は出版社から出てる書籍と違って校閲などが入っていないことが多く、内容の正確性という点でやや怪しさがあります。
(出版社から出てる書籍にも意見の偏りや誤字・脱字はありますが…)
また本人の知識の吸収や具体的な行動の変化が起きるかという点でもネットは読書に劣ります。
その一番の分かれ目が取得にコストがかかっているかどうかという点です。
ブログやYouTubeの情報はタダで気軽に見られるのがメリットの1つですが、それを得るためのコストという痛みを伴いません。
そのため「頑張って吸収しよう」「内容を日常に活かそう」という意識が生まれにくいのです。
もちろん値段が高ければ良いというわけじゃありませんが、ネットの情報は吸収意欲が薄れやすいことは覚えておきましょう。
2-2 モノの見え方は人によって違う
もう1つ着眼点や重要なポイントは人によって異なるということです。
同じ本を読み返してみると、前回はあまり意識しなかった一節に目が留まることがあると思います。
知識の習得などによって解釈が変わった、理解できるようになった等の要因もありますが、最もシンプルな理由はアンテナの変化です。
これは心理学や脳科学の領域ではカラーバス効果と言われています。
自分がその時に必要だと思う情報に対してアンテナの感度が高くなり、優先的に関連情報をキャッチするようになる脳の働きのことです。
本の要約などは主にその作成者のアンテナを基準にまとめられています。
つまり、その人にとって重要と思えるポイントをピックアップしているため、必ずしもその内容が自分にとっても重要とは限らないということです。
実際に本を読んでみたら、要約ではカットされていた重要なポイントが見つかる可能性もあります。
配信者もなるべくバランスよく要約しようと心掛けてるとは思いますが、どうしても多少は主観が混じってしまうモノです。
こうしたメディアは本選びのキッカケの1つにはなりますが、最終的には自分の目で本を読むことをオススメします。
3 意義のある本の選び方

書店や電子書籍ストア、図書館を覗くと、非常に膨大な数の本があることが分かります。
つまりそれを片っ端に読もうとしてたらいくら時間があっても足りません。
お恥ずかしい話ぼく自身も最初の頃は、どれだけ多くの本を読むかが目的になってました。
長い通勤時間を有効活用することに躍起になっていた結果でしょう。
読みたい本が次々に出てきて追いつかず、また似たような内容の本を何度も読んでいる現状に気付いたところで、本の選び方を見直す必要性を感じました。
3-1 本を読む目的を設定する
本を読むこと自体が目的になっていて、読んでそれで終わりって人は昔のぼくだけじゃないはず。
もちろん面白い研究とかを娯楽感覚で読むのもOKです。
しかし有意義な時間の使い方の観点からは何かしら少しでもいいから収穫を得た方が良いと思います。
そのためにもその本を読む目的を明確にしておくのが重要です。
何を学ぶことを目的にして読むのか、それを意識することで情報の取捨選択や吸収効率も大きく変わります。
人間の脳には自分が求めている情報を優先的にキャッチし、記憶に定着しやすくなるという特性があります。
既に紹介したカラーバス効果(選択的注意集中)という脳の特性です。
こうした効果は、目的を定めず漫然と読んでいるだけでは得られません。
目的を持つことには、せっかく効率的なはずの読書を非効率なものにしてしまうのを防ぐ効果もあるのです。
3-2 様々な視点から見る
フラットな視点で自分の考えを整理するためには、情報や意見の偏りを無くすことが必要です。
人間には確証バイアスという特性があり、どうしても自分にとって都合の良い情報に目が向きやすくなります。
例えばあなたが「お金で幸せは手に入らない」と考えていたとすると、「お金で幸せは買える」という主張の本にはなかなか手が伸びません。
考えを変えるというのは苦痛や労力を伴うので、脳が現状の考えに留まらせようとするのです。
そんな風に自分の主張に近い本ばかり読んでいたら、その考えを強化するだけで一向に進歩も変化もありません。
「自分の意見はやっぱり正しいんだ」という自己満足のためなら、読書をする時間も本を買うお金もハッキリ言ってムダです。
様々な視点・立場の本を読むことの意義は、フラットな判断の素地を作るだけではありません。
この読み方は、どんな立場の著者でも共通して書かれていることがあると気付けるのです。
どんな立場だろうと同じということは、その分野において普遍的な事実であると言えます。
またいきなり専門書から読み始めても挫折が見えているので、基礎~入門~応用などとレベルを分けて本を選ぶことも重要です。
4 効果的な本の読み方

自分の目的に適った本を選べたらあとはひたすら読むだけでOKかと言うとそうではありません。
どんなに目的を明確にして書籍を絞り込んだとしても、検索結果は相変わらずの膨大さです。
つまり読む時点でも効率性を考えなければ、忙殺されることになります。
そこで重要になるのが目次を最初に見るということです。
本はどうせ頭からケツまで通しで読むからと、目次を飛ばす人は少なくないんじゃないでしょうか?
しかし本の目次はかなり重要で、ポイントは主に以下の3つです。
①全体の流れを把握できる
②不要なところ、知ってる部分を読み飛ばせる
③記憶が定着しやすくなる
また目次のほかに2つ読み方にポイントがあるので、併せて4つ以下で紹介します。
4-1 速読のキモは早く読むことではない
多量に本を読む人は全員が読むのがメチャメチャ速いわけではありません。
特殊能力を持っていないのに読むのが速い人の多くは、自分にとって必要なところだけ拾い読みをしています。
目次は全体の流れを把握して主張の傾向を掴み、その上で自分が知らないところを選ぶのに非常に重要です。
完璧主義で、どうしても通しで読まないと気が済まないという人は多いと思います。
しかし既に知ってる知識をわざわざ時間をかけてなぞるのは非効率です。
お金を払って買ったのに勿体ない気もするでしょうが、時間の方がもっと貴重ということを肝に銘じておきましょう。
ただ答えの部分だけを読むというのはあまりオススメしません。
論理の流れやメカニズムを抜きにして方法論だけを知っていても実用的な知識にはならないからです。
4-2 予測と裏切りで脳への刺激をアップする
何故目次を読むことで記憶に残りやすくなるかというと、意外性・裏切りを経験できるからです。
目次を読んで、書いてあるであろう内容を予備知識から推測しておきます。
そして実際読んだ時、大抵の場合は自分の想定がいい意味で裏切られるはずです。
これは脳科学の領域では偶有性と言われており、強く脳を刺激することで本の内容が記憶されやすくなります。
偶有性は同時に前頭葉の発達も促すため、ロジカルシンキングや自制心、集中のアップにも効果的です。
これは目次から各項目に書かれているであろう事前に内容を推測しておかないと経験することが出来ません。
予測するにはそれなりの予備知識、読書量が必要ですが、読書が習慣になると容易にできるようになります。
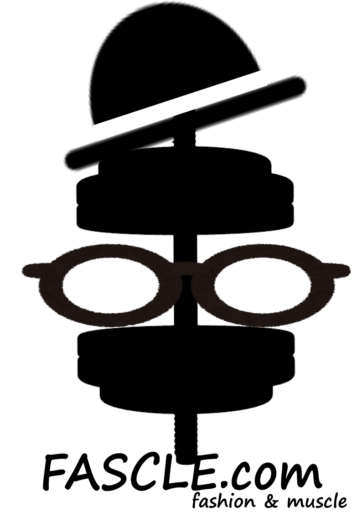
目次は目的通りの本かを確認する上でも重要だよ
4-3 マーカー・ブックマーク
そして次に効果的な読み方がマーカーやブックマークをしながら読むことです。
重要なポイントが出てくるたびにノートに写していたのでは読書のリズムが崩れてしまいます。
物事を効率的に進めるのに重要なのはスピードでなく、テンポです。
このことについてはこちらのページで解説しています。
そこで気にあるポイントがあったら、マーカーや付箋を貼っておくようにしましょう。
復習の際はこのマーカー・付箋部分だけをさらえばOKなので、非常に効率的になります。
この点で個人的には紙の書籍よりも電子書籍がオススメです。
ドラッグするだけでマーカーが引けますし、ワンタップで付箋を付すことも出来ます。
またこれらを一覧でまとめてくれるので、視認性がアップし探す手間も無くなるので非常に効率的です。
確認が終わった情報はマーカーや付箋を解除すれば一覧から簡単に消去できます。
こうした作業は紙の本では出来ないので、電子書籍ならではの強みです
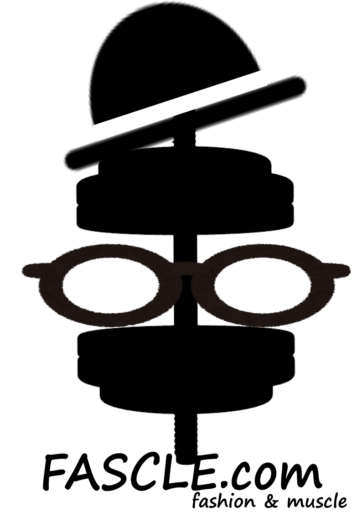
シンプルに場所も取らないしね
自分がその本で得た新たな知見にフォーカスすることは、行動の変化や情報のシェアなどアウトプットが前提です。
このアウトプットが先にあることで記憶の定着がより効率的になり、読んだ時間をムダにしなくなります。
4-4 見切りをつけることも重要
目的を明確にして、目次などを見て慎重に本を選んでもたまにハズレということはあります。
そういう本でも何となくお金や、これまで読んできた時間がもったいない気がして読み続けてしまう人も多いでしょう。
これはサンクコストバイアス(埋没費用)と言って、これまでかけた投資がムダになってしまうことを嫌う性質のことです。
つまらないと思った映画を途中で止められないことや、負けが込むほどに台から手が引けなくなるパチンコなどが分かりやすいでしょう。
これまでかけた時間やお金は既に失われ、読み進めたからと言って帰っては来ません。
むしろそのまま読み進めることで、ドブに捨てる時間がドンドン増えていくだけです。

ここから先に革新的な話があるかもしれないじゃん
このように期待してしまうものですが、しっかり構成が練られた本なら序盤で興味を引ける内容・結論を持ってくるものです。
中盤くらいまで読み進めてイマイチなら、ほとんどの場合その先はさらにトーンダウンしていきます。
つまり時間の価値が今まで以上に低くなっていってしまうということです。
既に述べたとおり、時間の方が圧倒的に貴重な資産なので、さっさと見切りをつける勇気も持ちましょう。
4-5 休むのもまた重要
沢山の本を読むことは非常に良い習慣ですが、あまりインプット一辺倒になるのは考え物です。
というのも脳はマルチタスクが出来ないため、情報のインプットと整理を同時には出来ません。
つまりインプットが続いている間は整理が全く進まないということです。
脳のワーキングメモリはあまりキャパが大きくないので、整理する時間を与えてあげないと情報がオーバーフローしてしまいます。
どれだけ読書に時間をかけても、ほとんどが記憶に定着してくれないということです。
アイデアのタネとしてインプットは重要ですが、整理やアウトプットをする時間をとるためにもたまには休みましょう。
手を止めて休むこと、すなわち無意識の力は非常に強力です。このことについては以下のページで解説しています。
まとめ
読書をするメリットから、本の選び方、読み方まで解説しました。
人一人の人生で経験し考えられることはたかが知れていますし、偉人や成功者に直接会って話を聞くことは困難です。
しかし本はその限界をたった数千円で越えさせてくれます。図書館で借りればなんと無料です。
とは言え手当たり次第に本を読めるほどの時間もやはりありません。
吸収したい知識や技能など、読む目的を明確にし目次や要約メディアを通じて自分に必要な本を選び出します。
単に自分にとって耳障りの言い情報を聞きたいがために本を読むなら時間とお金のムダなので読む必要はありません。
そして自分にとって得るものがないと思った本はサンクコストバイアスに囚われずに容赦なく切り捨てるようにしましょう。
もっと有益な本があるのに、払ったお金惜しさに無益な本で時間を浪費するのは非常に愚かな行為です。
ぜひ自分の人生に影響を与える有益な本に沢山出会ってください。
てなとこで。
参考文献
学びを結果に変えるアウトプット大全 樺沢紫苑 サンクチュアリ出版

学び効率が最大化するインプット大全 樺沢紫苑 サンクチュアリ出版

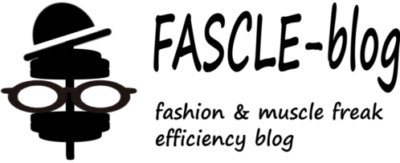






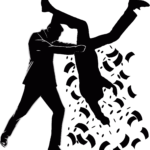








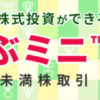

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません